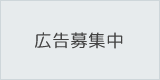歴史
有明海と八代海の接点に位置する本地域は海の交通の要として、古くから海人(あまびと)が支配したと見られ、県内有数の装飾古墳が散在しています。
江戸時代以前のいわゆる天草五人衆の時代、大矢野と松島は大矢野氏、龍ヶ岳と姫戸は栖本氏に属していました。
天草島原の乱のあと、幕府は寛永17年5月天草全域を直轄天領として、旗本700石鈴木重成を天草代官として派遣、鈴木重成は寛永18年、全島に1町10組(86カ村)を置き、富岡代官所でこれらを支配しました。同時に、各組に大庄屋、各村に庄屋、年寄、百姓代を設け、行政機関としてこれらを整備しました。
慶応4年8月、天草は天領から長崎府の管轄になり、明治2年12月全島改めて40カ村に整備統合されました。
そのあと、明治4年、天草は八代県に編入され、次いで明治6年1月肥後国白川県(現在の熊本県)の管轄になりました。
昭和29年から31年にかけての、いわゆる「昭和の大合併」により大矢野町、松島町、龍ヶ岳町が誕生し、昭和37年に姫戸町が誕生しました。
昭和31年に雲仙天草国立公園に編入され、昭和41年9月に天草五橋が完成したことにより、観光地として大きく脚光を浴びるとともに、社会基盤の整備が進み、各種産業の発展に大きく寄与することとなりました。
平成11年に天草空港が開港、さらに平成14年に熊本天草幹線道路(地域高規格道路)が一部開通し、広域交通の利便性が向上しています。
平成16年3月31日に天草の玄関口として結びつきの強かった天草上島4町(大矢野町、松島町、姫戸町、龍ヶ岳町)が合併して上天草市が誕生しました。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月1日 上天草市の特命係長『上天草 四郎くん』を紹介します
- 2022年4月1日 上天草市全図(管内図)について
- 2018年1月1日 位置と情勢
- 2012年11月28日 市章
- 2012年11月28日 市の花・木・鳥
- 2012年11月28日 市民憲章





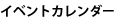

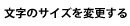

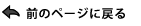


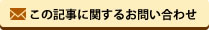
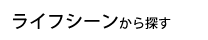




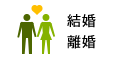

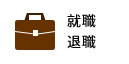


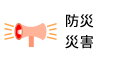
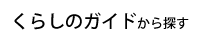

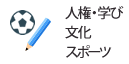

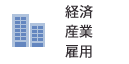



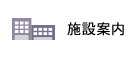

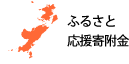

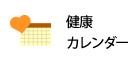







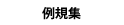

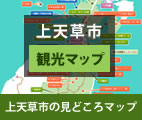

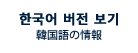
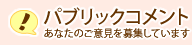
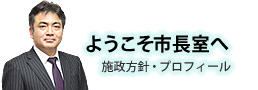


 QRコードを読み取ることで携帯版上天草市のURLが表示されます。
QRコードを読み取ることで携帯版上天草市のURLが表示されます。